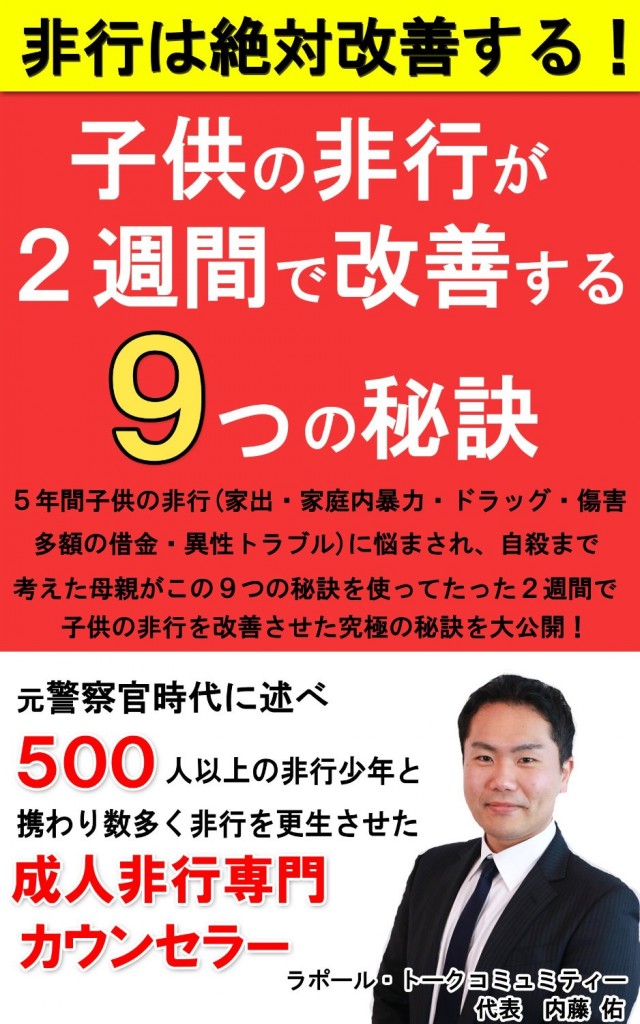
こんにちは。
あなたは、自分の言葉が子供の心に響いていないと感じるときはありませんか?
常に100%自分の言葉が相手に響きことはありませんが、
『相手に言葉が響かない時もある』
ことを忘れていると、足元を救われることを今回はお伝えしておきますね。
今年も2学期の始業式があった9月1日、そして授業が開始される9月4日に関東で報道されただけでも4人の学生が自ら命を断ちました。
遺書を遺した子もいれば、親に別れの電話をして断った子もいる。
夏休みの宿題が終わっていないことを親御さんに叱責された後に飛び降りた子もいれば、将来に悲観して断った子もいる。
何としても少なくしていきたい問題ではありますが、そのうえで見落としがちなことがあります。
よく学校の問題について悩んでいる子供に対して
『行きたくなかったら行かなくてもいい』
『学校だけが全てじゃない』
などとフォローを入れることを促していますが
≪親御さんが本心からそう想っていること≫
が前提条件となります。
前期のような言葉をかけておきながら、目や声の抑揚では
『学校に行った方が良い』
『学校を出なかったらこの先どうするの』
などという
≪言動の不一致≫
がおきると、最悪の結果に繋がる可能性があります。
感受性と責任感が強く、自分の二面性を出せない子は相手(親)が発する言葉が本心かどうかを見抜く力は親以上に長けています。
子供の命を守りたいのであれば、子供のどのような問題に対しても柔軟に受け止めて、闇を共感して光に導くだけのマインド(力)をつけておくことが特に現代社会には必須であると私は現場経験から感じています。
気合いと根性、世間体や一般的という視点だけで切り抜けられるほど甘くはありません。
また、子供に都合が悪い情報をシャットダウンできた時代ももう終わっていますので、綺麗ごとだけで立ち直るほど単純でもありません・・・が、本当の意味での人間力が親御さんたちが試されている時代でもあります。
先日、家庭内暴力や学校での暴力問題に悩むお母さんと話した時に、暴力の話題になりました。
『暴力は良くない』、『話せば分かり合える』・・・確かにそれは理想的なことですが、じゃあなんで人気アニメの描写によく暴力の描写が使われているのでしょうか?
なぜヒーロー番組に暴力が必要なのでしょうか?
本当に暴力がよくないのであれば、こうしたことについても親御さん一人一人が自分なりの答えを持っていた方が良い時代です。
子供たちの『なぜ?』に「一般的には」とか「普通は」などという切り返しが通用しなくなってきていることをヒシヒシと感じていますので、何かの参考になれば幸いです!

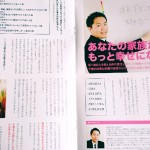

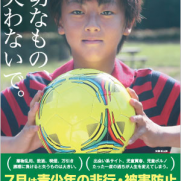













この記事へのコメントはありません。