
【Q 子供が心を開いてくれない場合の対処法は?】
19歳なる娘は2年位前から私に何も話さなくなりました。
物心つくころから
「ねぇ、お母さん聞いて、聞いて」
などとよく言っていたことを想いだし、その時は娘の話を聴いていたと思っているのですが、現状をみれば子供が悩んでいるときに子供の声に耳を傾けられていなかったのかもしれないと思っています。
子供が心を開く為にはどうすればいいでしょうか?
【A 先ずは親であるあなたが心を開いて下さい】
親子関係に限らず、相手に心を開いてほし良いのであれば
人として対等
に接することはもちろんですが
自らが心を開いて一方的に信頼すること
をしなければ、かなり厳しいですよ。
一見、子供が一方的に心を閉ざしていますが、お母さんご自身が同じような生き方をされてはいませんか?
「心を開いているつもり」は「心を開いてはいない」ということを覚えておいてください。
また、人の話を「きく」という言葉には3つ種類があります。
有名な話なので耳にしたこともあるかもしれませんが、「きく」には
聞く
聴く
訊く
がありますよね。
子供が非行にはるなど、子供との信頼関係が築けていない親御さんは、子供が小さい時から子供の話を
「聴く」ではなく「聞く」
であった(今も)可能性は高いです。
「聞く」とは上辺だけで耳に入れているので、相手のことは考えていません。
ですが「聴く」はしっかりと相手に寄り添い、話を「受け入れる」ということですので、この「聴く」が子供が小さい時からできていたのであれば、親子関係が悪くなることはあまり考えられません。
理由はいくつかありますが、分かりやすく言うと相手の考えを受け入れる、相手の立場に立てる人は
自分の軸があり、心に余裕があるから
です。
自分の人生で精一杯で心に余裕がなくなると、他人への承認欲求は高まり
見返りを求める人間関係
になってしまうので、例え相手が子供であろうともシャットダウンして「聞く」ことしかしなくなるのです。
そのような親御さんの「きいてるよ!」は「聞いて」はいますが「聴いて」はいないです。
子供との信頼関係構築が上手くいかない親子の会話に「聴く」はあまりなく
「聞く」もしくは「訊く」
が中心になっているため、当然ですが信頼関係は失われていきますよね?
ちなみに「訊く」は縦の人間関係をイメージしていただくと分かりやすいと思います。
警察官と犯人とか裁判長と被告人とか・・・。
子供に対して怒りや感情的に叱るときに、この「訊く」は出てきます。
過去に遡って子供の話をあまり「聴いて」来なかったのであれば、今から「聴く」に徹することが大切ですが、その前にお母さんご自身が
自分自身の心の声をしっかりと聴いてください
これをやらない以上、子供の声を「聴く」ことは難しいので。
子供や他人に意識が向かう時こそ「自分自身」に意識を向けてください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■
非行、ひきこもり、不登校など
あたなの悩みにお答えします!
詳細はこちらよりメール下さい。
ご相談はこちら
■□■□■□■□■□■□■□■□■



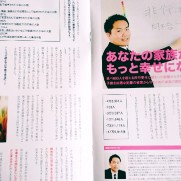













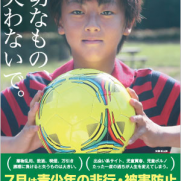
この記事へのコメントはありません。